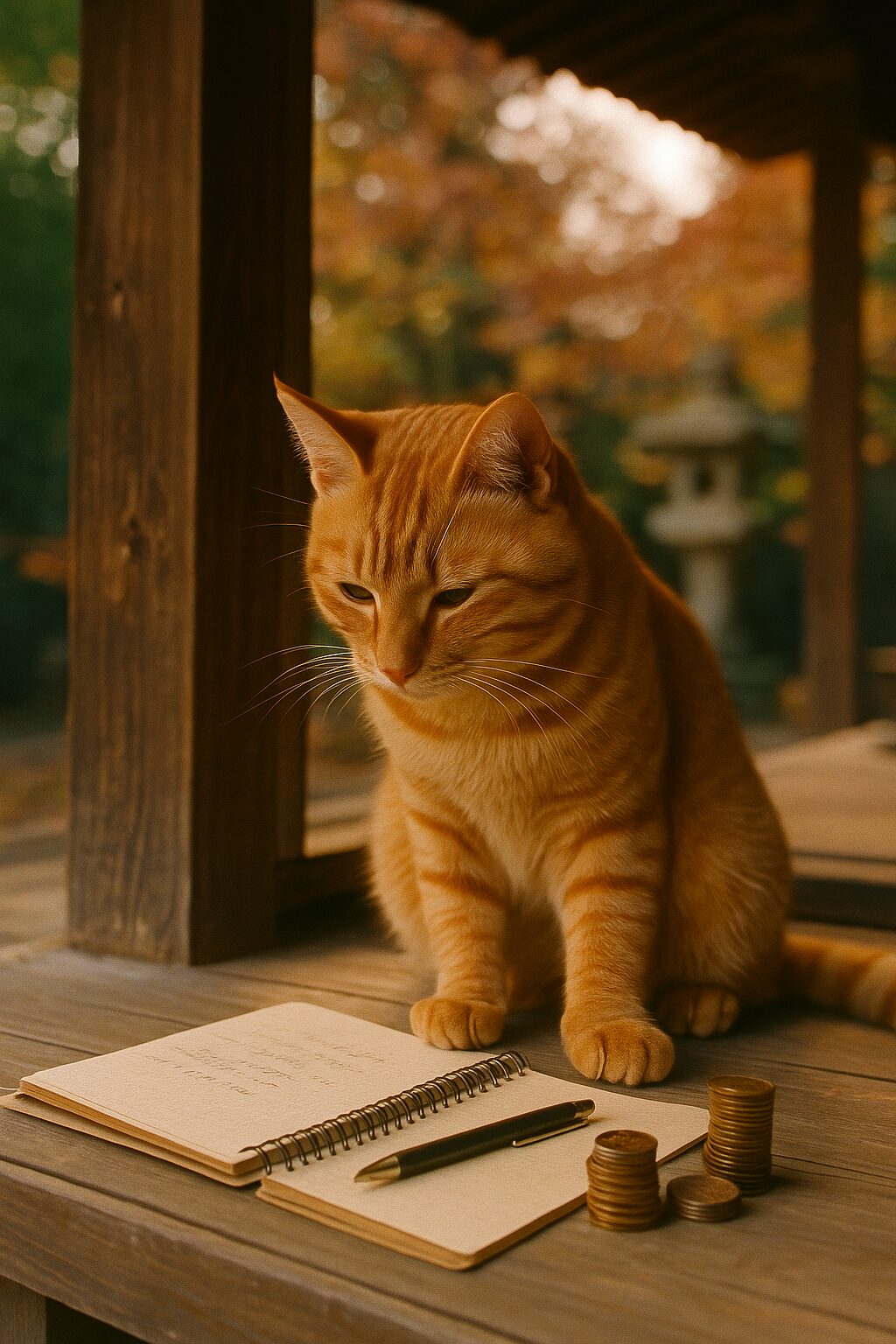そもそも「株式」って何?
お金を集めるために生まれた“人類の知恵”の物語
「株式」と聞くと、なんだか難しくて、投資家やお金持ちがやるもの…というイメージを持つ人が多いかもしれません。
でも実は、株式の仕組みは“人類の知恵の結晶”ともいえる、とてもシンプルで合理的な発明なのです。
その始まりは、今から400年以上も前のヨーロッパ、オランダで生まれました。
当時のヨーロッパでは、「大航海時代」と呼ばれる時代。人々は船で遠くアジアやアフリカへ向かい、香辛料や金、銀などを求めて長い旅をしていました。
しかし、航海には大きなリスクがつきものです。嵐で船が沈むこともあれば、海賊に襲われて積み荷を奪われることもありました。
それでも、もし成功すれば莫大な利益が得られます。
でも――その旅に必要なお金は、とても個人では用意できません。
船を作る費用、乗組員の給料、食料や装備・・・すべてにお金がかかります。
1人の商人が全部を負担していたら、失敗したときにすべてを失うことになります。究極の「ハイリスク・ハイリターンです」
そこで考え出されたのが、「みんなでお金を出し合って、成功したら利益を分け合おう」という仕組み。
これが「株式会社」の原型なのです。
1602年(日本でいう江戸時代)、オランダに「東インド会社(とういんどがいしゃ)」という会社が設立されました。
世界で初めての株式会社といわれています。
この会社では、多くの市民が少しずつお金を出し合い、その代わりに「株券」という紙を受け取りました。
これが、今の「株式」です。
そして、航海が成功して利益が出ると、出資者は自分の持ち分に応じて「配当金」を受け取ることができました。
つまり、株を持つ人は“お金を貸す人”ではなく、“事業の仲間”**だったのです。
これは当時としては、非常に画期的な仕組みでした。
この方法によって、大きなプロジェクトを進めるためのお金をスムーズに集められるようになり、世界の貿易は一気に発展しました。
そして、出資者たちはリスクを分散しながら、会社の成長とともに利益を得ることができたのです。
やがてこの考え方はイギリス、フランス、アメリカへと広がり、「株式市場」や「証券取引所」が生まれました。
証券取引所とは、株を売ったり買ったりする場所のことです。
こうして、世界中の人が企業の一部を所有できる時代が始まったのです。
日本にこの仕組みが伝わったのは、明治時代。
文明開化のころ、鉄道や造船、銀行などを設立するために多くの資金が必要となり、「株式会社」という形が広まりました。
たとえば三菱、日立、住友など、今も残る大企業の多くは、この時代に誕生したのです。
そして現代。
楽天証券やSBI証券といったネット証券が普及した今ではスマホひとつで、誰でも数千円から企業の株を買える時代になりました。
かつては一部のお金持ちだけのものであった「株式」が、今はすべての人に開かれた仕組みになったのです。
株を買うということは、その会社の“オーナーの一人になる”ということ。
企業が成長し、利益を上げれば、あなたにも「配当金」や「株価の上昇」という形でその成果が返ってきます。
つまり、株式は「投資家のためのゲーム」ではなく、「社会を動かす力をみんなで支える仕組み」なのです。
そして、「高配当株投資」とは、この古くから続く“利益の分かち合い”の考え方を今の時代に活かした方法です。
企業が稼いだ利益の一部を安定的に配当として出す――それを受け取ることで、あなたの生活も少しずつ豊かになっていく。
400年前に生まれた株式という知恵が、いま、あなたの将来を支える力になる。
そう考えると、投資はぐっと身近に感じられるのではないでしょうか。
次回は、特に役立たない知識・・・昔の株券はどんなものだったのかについて解説します!